マイボート釣りでのアンカリングについて、詳しく解説していきます。
この記事では、船舶免許の教本にあるような危険回避のためではなく、釣りのための実践的なアンカリングの方法を、初心者にも分かりやすく解説します。
アンカーの動作原理
なるべく難しい話はなく簡潔に書きたいのですが、アンカーを効率よく使うためには最低限、動作の理屈は理解しておきましょう。
重さで止めているわけではない
アンカーの効く原理は、爪が海底の砂や泥に食い込んだり、岩に引っかかったりして効きます。このアンカーが効く力の事を把駐力といいます。
もちろん大きく重たいアンカーの方がよく効くのですが、あくまで爪が海底に刺さって止まる仕組みになっているので、コンクリートブロック等の簡易的な物では、重いだけで全く効きません。
また、ゴムボート等で使われるマッシュルームアンカーのように、深くまで刺さらない形状の物も風が強いと流されてしまいます。
効率の良いアンカーの使い方
海底が岩礁地帯の場合は、適当に打っても岩に引っかかりしっかりと効くのですが、砂地でのアンカリングは、少しコツが必要です。
どの様な形状のアンカーであっても、基本は爪を海底に食い込ませるようにアンカーを打ちますが、この時にアンカーロープをなるべく長く出すようにします。
海底に対して出来るだけ平行に引いた方が、アンカーを海底から引き離す力が弱くなるため、同じアンカーでも強い把駐力を得る事ができます。
ちなみに、小型船舶の教習で、風が強い時には水深の5倍のロープを出すと教えられました。
釣りためのアンカー用品
アンカーの動作の仕組みと、効かせ方について簡単に書きましたが、アンカーを打って釣りをするためには、ピンポイントで漁礁の真上に着けなければいけません。
これが結構難しいです。小さなポイントだと、10mズレただけで釣れないと言ったこともよくあり、水深が深くなればなるほど難しくなっていきます。
なのでまずは、なるべく簡単にアンカーを打てるよう、初心者こそしっかりとしたアンカー用品を揃えましょう。
アンカーの選び方
メインのアンカー本体については、ダンフォース型か唐人(フィッシャーマンズ)アンカーがおすすめです。
ミニボート前提ですが、以前書いた下の記事が参考になると思います。

ロープの先にチェーン
上でなるべく長くロープを出した方がよく効くと書きましたが、ピンポイントで止めたい場合は、ロープの長さをなるべく短くした方が良いです。短ければ短いほど、狙った場所に止めやすくなります。
またアンカーを中心とした半径が小さくなるので、風向きが多少変わっても、振れ幅が小さくなり、ポイントからもズレにくくなります。
しかし、ただ単にロープを短くしてしまうと、上で書いたようにアンカーを海底から引き上げる力が強くなり、効かなくなってしまいます。
そこで、アンカーロープの先端に金属のチェーンを数m付けます。
すると、チェーンが海中で重りになり、ロープから先がたわみます。これにより、チェーンを付けない場合と比べ、短いロープでも海底と平行に近い状態で引くことができます。
さらに、海底の岩にロープが擦れて傷んでしまうことの予防にもなります。
高比重のロープを使う
上のチェーンと同じ理由ですが、アンカーロープには高比重(重い)ロープを使いましょう。
ロープの材質は様々な物が販売されていますが、海水よりも比重の高いロープを使うことで、ロープ全体を海中でたわませ、より短いアンカーロープで使用することができます。
高比重のロープとして、「ポリエステル」や「クレモナ(ビニロン)」があり、どちらも耐久性に優れたロープですが、クレモナの欠点は水に濡れたり乾いたりを繰り返すと固くなってしまいます。
ボートのロープロッカーやカゴなどに入れる際に、ゴワゴワのロープでは扱いにくいので、個人的には固くならないポリエステルをおすすめします。
無駄に太いロープを使わない
アンカーロープの太さですが、販売店などで記載されている太さの目安というのは、かなり安全を見越した太さが紹介されている場合があります。
生死に関わる状態なら必要かもしれませんが、釣りに使うには潮流を受けやすかったり、ロープが海中で落ち着くまでの時間が掛かったりと、太すぎるロープはあまりいい事がありません。
ミニボートなら6mm程度、20ft台前半で10~12mmもあれば、強度的には十分だと思われます。
アンカーロープの長さ
使う海域の水深によりますが、目安としては水深の3倍あれば、全く問題ないと思います。
上で、風が強い日には水深の5倍と教えられた、と書いていますが、あれは安全を見越しすぎです。
風が強い日は出ないと決めているなら、2.5倍くらいが良いかと思いますが、実際に使ってみないと正確な数字は分かりません。
収納スペースに余裕があるなら、3倍程度あれば問題ないでしょう。
アンカーの打ち方
基本的なアンカーの打ち方は、ポイントの風上側にアンカーを打ってロープを伸ばし、ポイント上でロープを固定します。海底が岩でも砂でも同様です
ただ、余程大きな漁礁でない限り、海底が砂の場所にアンカーを打つことになるかと思います。これは、アンカーロープを海中で斜めにしないとアンカーが効かないためです。
しかし、砂地の場合、ロープが短すぎると走錨(アンカーが効かず流されてしまう事)してしまう事もあり、逆に長すぎると微妙な風向きの変化でアンカーを軸に大きく振られてしまいます。
アンカリングのコツは、風向き(流される方向)と、ロープの長さです。
1. GPSで場所を確認
始めに、ピンポイントでボートを止める為には、アンカーを入れる前にGPSでポイントを確認しておきます。
マークを入れたり、カーソルを表示したりして、しっかりと予定ポイントが判るようにしておきましょう。
次に潮の流れの緩やかな場所であれば、ボートを止めて風向きを確認します。この時にGPS画面上で風向きが分かるように、コンパス等で確認します。
潮がかなり早い場合や、風向きが分かりにくい時は、めんどくさいですが一度数十m流されてみて、どちらに流れるかを同様にGPS上で把握しておきます。
かなり重要なポイントなので、正確に確認するのがコツです。
2. 必ず風下から進入
風向きや流される方向が分かれば、GPSの画面を見ながら正確に風下側(流されて行く方向から)ポイント真上を通過します。
この時に左右に進路を変えるとズレてしまうので、一直線でポイントを通過できるようにします。
3. アンカーの投入の位置
ポイント上を通過した後、風上(流される方向と逆)側にアンカーを打ちます。
どの程度の距離を進んでアンカーを入れるかは、水深や風速、ボートの大きさ、使っているアンカーによっても変わってきます。これは各自で試してみるしかありませんが、目安としては下のような感じです。
快適に釣りが出来る程度の微風であれば、水深と同じだけの距離を進めば、問題なく効かせられるかと思います。
この場合、単純計算でロープの角度が45°になりますが、微風で流される力が弱い場合には、ロープやチェーンの重みでかなりたわんでいるため、アンカー接続部では水平に近い状態となっています。逆に、ボート側では、ほぼ真下に落ちているように見えます。
風が強い場合や、潮が速い時は水深の倍程度進んでから投入してみましょう。強風では引っ張る力が強く、ロープがあまりたわまないため、微風の時よりロープの角度が必要になります。
この通り過ぎる距離の考え方としては、水深の〇倍と言うのが基本です。
つまり、水深20mでポイントから20m離れてアンカー打って問題なく効いた場合、
水深40mでは、同じくらいの風なら40m離れてアンカーを打てば効かせられると言う事です。
上の場合は、水深の1倍です。
どのくらいの風で、何倍の距離を通り過ぎればいいと言うのを、自分で試して覚えておきましょう。
4. ポイント真上に止める
以上の手順でアンカーを投入すれば、角度的にはほぼピッタリ行くかと思います。
最後にポイントの真上へ移動しますが、これは後進しながらロープを出して行きます。
アンカーが着底する前に後進しても大丈夫ですが、その場合、ロープが抵抗なく出るようにして下さい。途中で絡まったりモタモタしていると、アンカーがボートの方へ寄ってきてしまい、予定の場所に落とせなくなります。
後進のスピードは、なるべくゆっくりの方が良いでしょう。GPSで確認しながら徐々に合わせていきます。そのためには、上で書いたよりも少し多めにポイントを通り過ぎてから投入すれば、ロープの出し加減で微調節がやりやすくなります。
また、通り過ぎてしまった場合でも少しなら巻き取って戻る事も出来ます。
ただし、多くロープを出してしまうと、最終的にポイントからズレやすくなります。なるべくロープは出さない方が、風向きの変化で振られにくくなります。
まとめ
アンカー用品の選び方、実際の打ち方をなるべく詳しく解説してみました。
アンカーの打ち方をまとめると、
- GPS画面上で流される方向を正確に確認
- 流された方向から真っすぐポイントに進入
- ポイントを通り過ぎ、アンカー投入 通り過ぎる距離は風速により調整
- 後進でゆっくりポイント上まで移動して、ロープを固定
- 必要に応じて、ロープを繰り出しor巻き取り
ピンポイントでアンカリングする事は初めのうちはかなり難しいと思いますが、適当に打つのではなく順序立てて行えば、初心者の方でもすぐに出来るようになるかと思います。
また、アンカー用品をしっかりと効く物を揃える事が早道です。




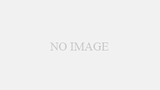
コメント